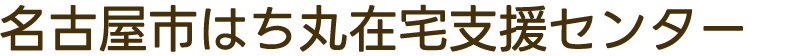ホーム > お知らせ一覧
2026.02.04
活動報告
令和7年度 多職種連携研修会(ACP研修会 基礎編)を開催しました
全市の多職種を対象に、令和7年12月11日(木)および令和8年1月17日(土)の計2回、「基礎編」を開催しました。基礎編のテーマは“多職種に共通する支援姿勢を学ぶ”です。両日を合わせ114名の多職種が参加しました。 講師の山岸暁美先生の講義タイトル「誰のための、何のための ACPなのか」の通り、ACPとは何か、どのようなことが目指されるのか、普段の支援とどう結びついているのかを、講義と多職種によるディスカッションを通して学ぶ内容でした。欧米でのACPに関する論文から近年の動向が紹介されたほか、地域でACPに取り組んでいくための方法や工夫について、他市町の実践も紹介されました。 グループワークでは、今年度より新たに、地域から募った多職種18名が各日のファシリテーターとして参加し、ワークのねらいに向けた理解が得られるようディスカッションをサポートしました。 アンケートには、「初めてのACP研修でした。自分や自分が関わっている方々のACPについて早い段階で話をする必要性について勉強になりました。今一度しっかり勉強したいと思いました」「他職種の方の意見がとても参考になった。ACPについて真剣に考えている人の話を聞くのはとても刺激になる」「ACPの理想論と現実の差を感じた」との感想がありました。また「医療や介護の現場では“死”の捉え方が一般とかけ離れていると思うので、それを理解したうえで関われるような研修があってもよいと思う」との声も寄せられました。 ACP研修会は、在宅療養者の生活と人生に関わる医療とケアのあり方を考え、医療・介護の多職種が協働することの意義を学ぶ機会となることを大切にし、開催しています。多職種の方々に広く参加いただけるよう継続して実施していきます。
続きはこちら対象エリア
市内共通
2026.02.03
活動報告
令和7年度 中区多職種研修会を開催いたしました
令和8年1月24日(土)、名城病院 地下1階 大会議室において「令和7年度 中区多職種研修会」を開催いたしました。中区の在宅医療・介護に携わる多職種の皆さま、総勢46名の方にご参加いただきました。 第1部は、「多職種の役割を知る「歯科医療」」について、藤井歯科医院 院長 藤井肇基先生にご講義いただきました。在宅における歯科医療の3つの役割や、多職種連携における歯科医師の役割など、明日からの在宅サービスの質の向上に繋がるような講義でした。また「ケアマネジャーという専門職の今と未来」については、居宅支援事業所 草まくら 管理者 主任介護支援専門員 三上祐一郎氏にご講義いただきました。ケアマネジャーは介護保険制度の要・総合調整役であることや、ケアの中心にあるのは、”つなぐ力”であることなど、専門職の業務内容や目線などについて、深く学ぶことが出来ました。 第2部のグループディスカッションでは、森内科クリニック 院長 森紀樹先生に司会・進行を務めていただきました。事例を基に、多職種連携について考える時間となりました。「普段やりとり出来ない職種の方々と専門的な意見を伺うことが出来ました」「在宅に関する経験や知識が乏しいため、事例検討により多職種の意見を聞くことが出来、非常に貴重な経験となりました」など、在宅や病院でご活躍される方々のご意見ご感想をいただきました。 今後も、多職種連携に携わる皆様の、相互理解のきっかけの場になるような研修会の開催を、事務局一同努めてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
続きはこちら対象エリア
中
2026.01.21
活動報告
中川区「訪問看護師とケアマネジャーとの交流会(合同委員会)」を開催しました
令和8年1月15日(木)、「訪問看護師とケアマネジャーとの交流会(合同委員会)」を開催しました。当日は、18名の訪問看護師と21名のケアマネジャーのみなさまにご参加いただきました。 この交流会は、「中川区訪問看護ステーション委員会」と「中川区ケアマネジャー委員会」との合同委員会も兼ねて開催。委員会の活動を知っていただくため、委員会に登録していない区内事業所にも参加の呼びかけを行いました。 第1部の合同委員会では、中川区在宅医療・介護研究会の報告や委員会の活動内容について紹介。第2部は交流会とし、グループに分かれて意見交換を行いました。 始めはみなさん硬い表情でしたが、時間とともに緊張もほぐれていった様子で、時折笑い声も聞こえる中、交流会では活発な意見交換が行われました。 終了後に実施したアンケートでは、「顔の見える関係づくりは大切」「他職種との連携をはかるため定期的な交流の場が必要」等の意見があり、今後の企画策定の参考にさせていただきます。 中川区訪問看護ステーション委員会と中川区ケアマネジャー委員会では、これからも地域の支援者のみなさまの声を受け止めた委員会運営を進めてまいります。
続きはこちら対象エリア
中川
2026.01.13
活動報告
令和7年度 天白区多職種連携研修会を開催いたしました
令和7年12月25日(木)14:00~16:30、天白区役所講堂にて、「~備えは”知る”ことから。医療・介護・行政・地域のつながり~ 災害時の役割・動きを相互理解しよう」と題し、研修会を開催しました。当日は計68名(参加者58名、登壇者10名)の皆様にご参加いただきました。 令和6年8月の宮崎県日向灘を震源とする地震発生にて、気象庁より初の「南海トラフ地震臨時情報」発表を受け、天白区では今年度、行政や多職種を交えて災害に関する取り組みを進めております。6月に、はち丸ネットワークを活用した災害時BCP模擬訓練を行い、訓練での課題から、先ず互いの状況や役割を理解する機会を設けるため、今回の研修会開催に至りました。 発災後の時期により対応が異なるため、時期を分けた構成とし、第1部では、発災直後から人命確保までの72時間について、天白区を対象とした災害対応に関し、区役所、消防、電力事業所、医師会による講演を、第2部では72時間以降の対応に関し、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護、居宅介護支援事業所、いきいき支援センターを交えた多職種シンポジウムを行いました。 今後も引き続き、より良い多職種連携に向けた取り組みを進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
続きはこちら対象エリア
天白
2025.12.03
活動報告
令和7年度 瑞穂区多職種連携研修会を開催しました
令和7年11月15日(土)、名古屋市立大学医学部研究棟にて「被災地支援経験者から学ぶ災害時の在宅療養者支援」をテーマに令和7年度瑞穂区多職種連携研修会を開催しました。当日は瑞穂区および近隣区の医療・介護関係者40名にご参加いただきました。 第1部シンポジウム「現場のリアルと今できる備えを考える」では、能登半島地震の際にJMATとして支援活動に参加された、西村内科クリニック 院長 西村賢司先生と、ひなた調剤薬局 管理薬剤師 近藤満里子先生より、救護活動をはじめとする被災地支援の体験談と、そこから見えた課題についてご講義いただきました。さらに、瑞穂区役所区政部総務課 課長補佐 防災担当 岡部将大氏より災害時における名古屋市の取り組みについて、みんなのかかりつけ訪問看護ステーション 訪問看護部長代理 災害対策室室長 災害看護専門看護師の大久保貴仁氏よりBCPの考え方や災害スイッチについてご講義いただきました。 第2部では、みずほ通りクリニック 院長 勅使河原修先生を座長に、事前にいただいた質問や当日の質疑をもとに、座長・講師と参加者によるディスカッションを行い内容をさらに深めていただきました。 研修会後のアンケートでは、「災害現場のリアルな状況を理解する貴重な機会となった」「水やトイレの備蓄やBCPの見直しなど、備えるべき事項を再確認できた」「災害スイッチONのタイミングを考えるきっかけになった」「市の取り組みなど具体的に情報を得ることができた」「自分自身の安全確保の重要性を改めて認識した」「業務に直結する具体的な提案が参考になった」など、多くの声が寄せられました。 今後も、在宅療養を推進する上でよりよい多職種連携を実現できるよう努めて参りますのでよろしくお願いします。
続きはこちら対象エリア
瑞穂
2025.12.01
活動報告
令和7年度 在宅医療研修会を開催しました
令和7年10月1日(水)から10月31日(金)までのオンデマンド配信にて、『災害への備え、「今」私たちにできること~被災経験から学ぶ~』と題し実施しました。 第1部 「震災の備えのBCP」 では、石川県能登町の小木クリニック院長 瀬島照弘先生に講師を務めて頂き、令和6年の能登半島地震でBCPを発動し、診療継続された体験をご講演いただきました。 第2部 座談会 では、名古屋市医師会 在宅医療・介護連携委員会より、委員長 亀井克典先生と、副委員長 任隆光先生にご参加いただき、講師との座談会を行いました。 参加申込者261名、視聴回数401回、アンケート回答者数84名でした。 アンケートの回答では、講義について「策定したBCPがどのように役立ったか、実例を交えた講義でわかりやすかった」「医療従事者として、発災時の対応について改めて考える機会となった」等の感想をいただきました。 座談会については、「地域での課題や、行政との課題が分かりやすかった」「職員の意識付けと日頃の訓練が重要と改めて感じた」等の感想をいただきました。 受講後具体的に取り組みたいことへの回答では、「BCPの見直し」「スタッフとの話しあい」等の、自事業所での取り組みについての意見を多くいただきました。その他、「連携体制の構築」「自治会との話しあい」「要援護者の自助への支援の徹底」「行政との話しあい」等の取り組みも挙げられていました。 ※研修動画および資料は名古屋市医師会員のみ下記「在宅医療研修会講演動画」から視聴可能です。(会員用ホームページへのログインにはID・パスワードが必要となります)
続きはこちら対象エリア
市内共通
2025.11.27
活動報告
令和7年度 北区多職種連携研修会を開催しました
令和7年11月15日(土)15:00~16:30、名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 2階大ホールにて「心不全患者さんを地域で支えよう」をテーマにした研修会(主催:北区在宅医療・介護多職種連携会議)を開催しました。土曜日午後の開催でしたが多くの多職種の方(40名)にご参加いただきました。 第1部では「心不全になると起こる身体の変化」について、いざわ内科・消化器内科クリニック総院長の井澤 伸一郎先生にご講義いただきました 第2部のグループワークでは、講義内容を踏まえ、病識があまりなく入退院を繰り返している患者さんの事例をもとに「じぶんカルテ」も活用し、課題の背景や要因、具体的な支援策等について多職種間でディスカッションしていただきました。 今後も、より良い多職種連携に向けた取り組みを進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
続きはこちら対象エリア
北
2025.11.20
活動報告
令和7年度 西区多職種研修会を開催しました
令和7年11月13日(木)14:00~16:00 当日は、講師として名古屋市保健所西保健センター田邊裕先生をお招きして、震災時の西区の被害想定や区民の生活の場、各団体の初動の考え方、各団体の役割と情報連携について講義とグループワークを行いました。 グループワークでは、所属機関に応じて医療、福祉、保健の3分野に分かれて協議を行いました。それぞれの視点で協議された意見を共有できる良い機会となり、参加者からも「率直な意見交換ができた」、「それぞれの立場からの意見を聞けて良かった」との感想が寄せられました。また、災害時における情報共有については、「情報の集約や方法、課題について考えることができた」、「情報の入手方法について漠然としていたものが少しはっきりしたように思う」との感想が寄せられ、有意義な学びの機会となったことが伺えました。 今回の研修を通して、様々な立場の多職種が情報連携について共通認識を持つことが、災害対応力の向上につながるのではないかと改めて感じました。今後もこのような機会を継続し、災害時における備えや地域の連携体制の構築を目指してまいります。
続きはこちら対象エリア
西
2025.11.11
活動報告
【中村区訪問看護ステーション委員会】訪問看護委員会と訪問介護委員会との合同委員会を開催しました
令和7年10月21日(火)17時より、中村区休日急病診療所にて、「第4回訪問看護ステーション委員会と第3回訪問介護委員会」との合同委員会を開催しました。 当日は22名の方にご参加いただき、本年度の取り組みについて各委員会から報告を行いました。また、中村区の在宅医療・介護連携推進会議の取り組みでもある「なごや在宅医療・介護連携ハンドブック」の〈在宅療養時〉における連携ポイントを、緊急時の対応として日頃良くある『看取り』『情報共有』の事例を通して、訪問看護より解説しました。解説後には、訪問介護からの連携における困りごとに対して訪問看護が答える場面もあり、日々の業務の質を向上させる上で非常に価値があったかと思います。 今回のグループワークで使用した2事例は、実際に訪問看護と訪問介護の両支援を受けており、寄り身近に考えれるものとしました。①「支援者への自助意識の働きかけ」として今できること、②今後、平時からの連携について、③具体的な災害・被災状況下での安否確認についてを、「なごやハザードマップ防災ガイドブック」「災害避難マップ」などを活用し話し合いをしました。主な意見として「サービス担当者会議で災害時のことを含めた話し合いが必要。また、災害時の役割分担まで決めておくこともスムーズな連携につながる」など活発な意見が多く出され、現場の視点に基づいた有意義な意見交換の場となりました。 今後、在宅療養において災害時の多職種連携は重要なテーマとなるため、継続して取り組んでいきたいと思います。次年度も是非、ご参加ください。
続きはこちら対象エリア
中村
2025.11.11
活動報告
令和7年度 多職種連携研修会(ACP研修会 実践編)を開催しました
11月1日(土)名古屋市医師会館で開催し、61名の多職種が参加しました。 実践編は、臨床倫理について認識することを通して、「療養者にとっての最善の医療・ケア」を、多職種が支援チームとして、実践的に考えることを学ぶ研修会です。 当日は稲葉一人先生によって、事例に基づくグループワークを挟みながら、臨床倫理の基礎とともに意思決定支援についての講義が進められました。支援者としての態度・考え方・判断に改めて意識を向け、「療養者・利用者がおこなう意思決定」を本当の意味で支援することについて、一歩踏み込んで考える内容でした。 終了後のアンケートでは、84%の多職種が「普段から臨床倫理に関する問題を感じている」との回答でした。その問題を個人に留めず職場やチームで共有し検討しているかを尋ねる設問では、病院よりも在宅支援を担う多職種において、「共有や検討をしていない」との回答がやや目立ちました。今回の受講によって問題への取組み意識が変化したかを尋ねる設問では、「大いに変化があった」「変化があった」との回答が93%でした。 研修の感想として、「相手の気持ちに本当に寄り添う大切さを改めて考える良い時間になった」「内容は難しいと思ったが、考え方が整理された。事例を使って考えられるのは具体的でよかった」「ACPを実践的に捉えることができた」「非常に勉強になり、価値観が広がった気がした。ディスカッションも楽しめた」等の記載がありました。 実践編は次年度も全市多職種を対象に開催を予定しています。 多職種連携研修会は、職種や所属、支援領域を越えた多職種との交流による気づきや新たなつながりを得られる機会でもあります。これからも開催を重ねて参ります。
続きはこちら対象エリア
市内共通